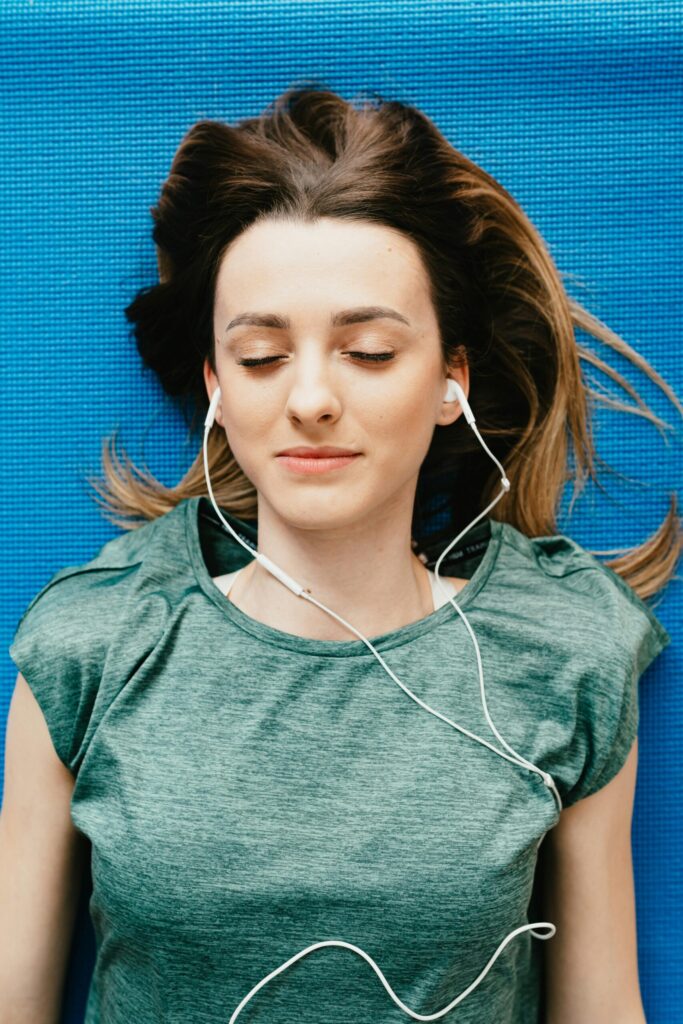現代人の無力感

この実験は、私たち人間の日常生活における様々な「諦め」の行動を説明しています。特に現代社会では、以下のような状況で学習性無力感が引き起こされやすいと言えます。
職場での努力が報われない
どんなに改善策を提案しても聞き入れてもらえない、または成果を出しても不当に評価されないといった経験が繰り返されると、「頑張っても状況は変わらない」という無力感を学習し、最終的にモチベーションを失い、燃え尽き症候群に陥ってしまいます。
不規則な環境
子育てや介護など、自分の努力では予測・コントロールが難しい事態が続く場合も、精神的なエネルギーが奪われ、「自分にはどうすることもできない」という諦めにつながります。
子どもの無気力
親や教師から過度に管理・干渉され、自分の意志で行動する機会を与えられなかった子どもは、自己効力感(自分にはできるという感覚)が育たず、無気力になりがちです。
克服のための考え方
幸いなことに、この「学習された無力感」は、逆の心理状態である学習性楽観主義(Learned Optimism)によって克服できることがわかっています。鍵となるのは、「失敗や困難に対する考え方の癖」を変えることです。
これは、精神療法の一つである認知行動療法の基本的なアプローチに基づいています。
ネガティブな解釈を変える3つの視点
困難な出来事(失敗)が起きたとき、無力感を「学習」しやすい人は、その原因をネガティブに解釈する3つの癖があります。
これらを意識的に修正することが大切です。
| ネガティブな解釈の癖 | ポジティブな解釈への修正(楽観的思考) |
|---|---|
| 永続性(ずっと続く) | 「一時的なものだ」 今回の失敗は単発的で、次の機会には変えられると考える。 |
| 普遍性(全てに及ぶ) | 「限定的なものだ」 この失敗は仕事の特定の部分だけで、他の能力や分野には関係ないと範囲を区切る。 |
| 個人化(全部自分のせい) | 「外的な要因もある」 自分の努力だけでなく、タイミング、環境、他者の行動など、コントロールできない外部の要因も影響したと考える。 |
失敗を経験した際に、上記の視点を用いて「本当に全部自分のせい?」「これは一生続くの?」と自問自答し、客観的かつ限定的な解釈を上書きすることで、無力感の学習をストップできます。
小さなことでも、自分で選択し、状況をコントロールできたという小さな成功体験を積み重ねることで、再び「自分には状況を変える力がある」という感覚(自己効力感)を取り戻すことができます。
学習性無力感のメカニズムを知ることは、諦めの連鎖を断ち切り、前向きな行動への一歩を踏み出すための強力な武器となるでしょう。
こころのかふぇ(ここかふぇ)
お問合せ info@kokocafe.jp
~名古屋から全国へ~
深刻化する前に、気づいて、つなぐ。
「こころも予防していますか?」
\ お気軽にご相談ください /
じっくり話したい: Zoom・チャット(予約制)
すぐに伝えたい: メール(予約不要)