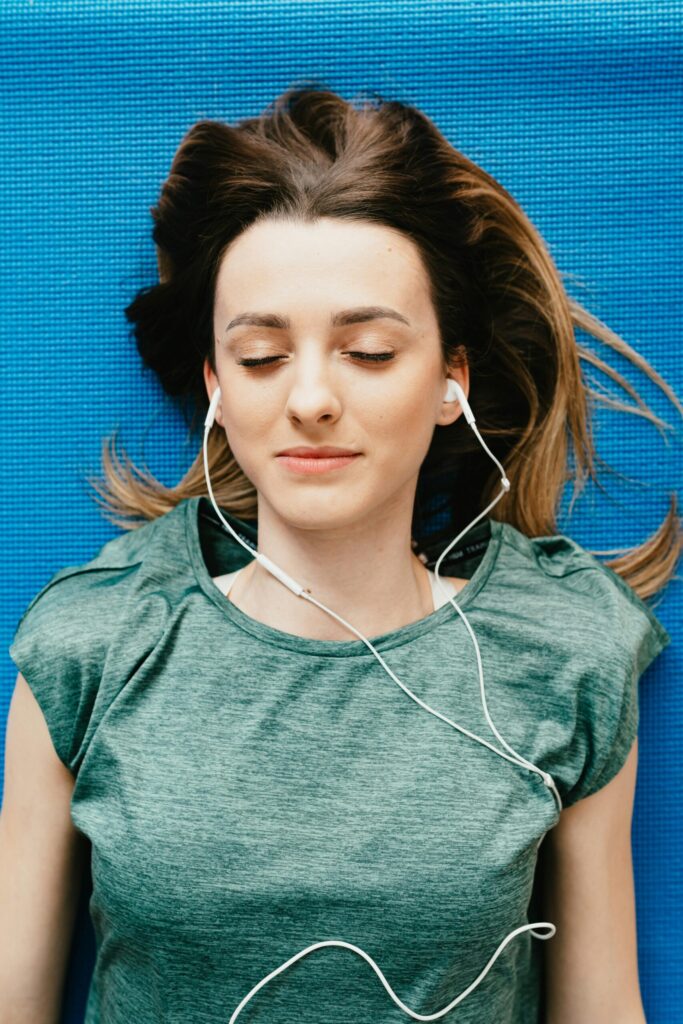劇場公開では興行的に振るわなかった作品が、Netflixなどの配信プラットフォームで大ヒットを記録します。この現象はもはや珍しいことではなくなりました。なぜこのようなことが起きるのでしょうか。そこには、映画と私たちの関係性を変え、人の行動心理や深層心理に深く働きかける、アルゴリズムの力が隠されています。この不思議な現象を紐解く鍵は、劇場という「公共の場」と、自宅という「私的な空間」での行動心理の違いにあります。
劇場での“失敗できない”心理

私たちはなぜ、映画館に行くのでしょうか。それは、非日常的な体験を求めているからです。しかし、その体験にはコストが伴います。
サンクコスト効果とプロスペクト理論
映画館のチケット代や交通費、ポップコーン代など、劇場での鑑賞には少なくないお金がかかります。このお金を払うという行為は、「この映画は絶対に面白い」という期待値への投資であり、もし面白くなかったらどうしようというリスクも伴います。この心理学的な効果をサンクコスト効果(埋没費用効果)と呼びます。
人は、一度支払った費用が無駄になることを極端に嫌います。そのため、多くの作品の中から「絶対に失敗したくない」という心理が働き、結果として有名俳優が出ている、高評価な作品、あるいはすでにSNSで話題になっている作品に選択が偏りがちです。
さらに、劇場という空間は、私たちに社会的なプレッシャーを与えます。ポップコーンを食べる音や笑い声、感動の涙など、他人の目を無意識に意識してしまいます。自分の好みが周りとずれていないかというプレッシャーは、万人受けしにくいニッチな作品や、事前評価が分かれるような作品への興味を抑え込んでしまうこともあります。
自宅での“気軽に試せる”心理
一方、Netflixでの視聴はどうでしょうか。月額のサブスクリプション料金を払えば、何本見ても追加料金はかかりません。これは、行動経済学でいうところのプロスペクト理論に当てはまります。人は利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛をより強く感じる傾向にありますが、Netflixではすでに費用を支払っているため、作品を選ぶ際に「失敗しても損失はない」という心理が働き、劇場よりも気軽に、未知の作品に手を出しやすくなります。
「ちょっと見てみて、つまらなかったらやめればいいや」という心理は、劇場ではなかなか働きません。この「気軽に試せる」という心理的な土壌こそが、劇場では見向きもされなかった作品に光を当てる第一歩となるのです。