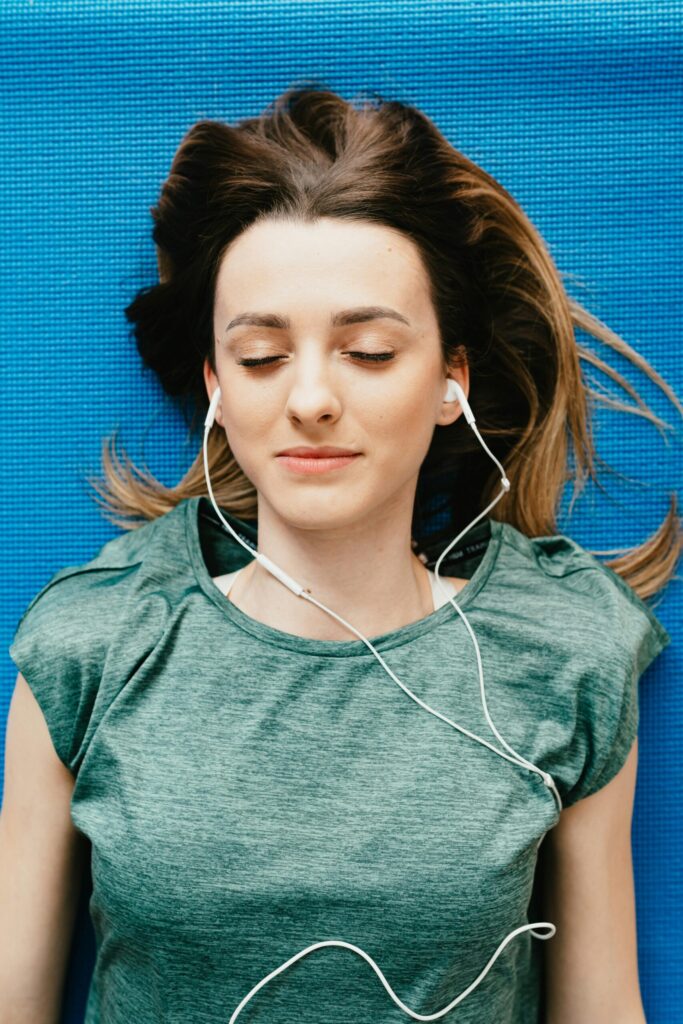有名な実験「つまらない作業の報酬実験」

認知的不協和を証明した最も有名な実験の一つが、1959年にフェスティンガーとジェームズ・カーレスによって行われた「つまらない作業の報酬実験」です。
実験の参加者は、1時間かけて非常に退屈な作業をさせられました。その後、彼らは次の参加者に「この作業はとても面白かった」と嘘をつくよう頼まれます。
- グループA 嘘をつく報酬として、わずか1ドルが支払われました。
- グループB 嘘をつく報酬として、多額の20ドルが支払われました。
実験後、参加者自身に「この作業は本当に面白かったか?」と尋ねました。
驚きの実験結果
驚くべきことに、1ドルしかもらえなかったグループAの参加者の方が、「作業は面白かった」と回答する傾向が強かったのです。
なぜか?
20ドルをもらった人
「嘘をついた」という自分の行動と、「作業はつまらない」という信念の間の不協和を、「20ドルという十分な報酬をもらったからだ」と簡単に正当化できます。彼らは矛盾を金銭で解決できたのです。
1ドルしかもらえなかった人
報酬が少なすぎるため、「嘘をついた」という自分の行動を正当化できません。この強い不協和を解消するために、彼らは「嘘をついた」という事実を変えるのではなく、「つまらない」という自分の信念の方を変えました。「この作業は、実はそんなにつまらなくはなかった。むしろ面白かった」と考えることで、自分の行動を肯定したのです。
この実験は、報酬が少ない方が、より強く信念が変化するという認知的不協和の核心を鮮やかに示しました。
日常生活に潜む認知的不協和
認知的不協和は、特別な状況だけでなく、私たちの日常生活のいたるところで働いています。
ダイエット中の誘惑
「ダイエット中は甘いものを食べてはいけない」とわかっているのに、目の前に美味しそうなケーキがある。
- 不協和の解消
「今日だけなら大丈夫」「明日から頑張ればいい」「このケーキはストレス解消になる」と考えることで、自分の行動を正当化する。
高価な買い物後の後悔(バイヤーズ・リモース)
奮発して高級ブランド品を買ったものの、「本当に必要だったのか?」「もっと安くてもよかったのでは?」と後悔の念がわく。
- 不協和の解消
「この品質なら長く使える」「他の人とは違う、特別なものを手に入れたんだ」と考え、自分の選択を正当化する。多くの企業が購入後に感謝メールや製品の優れた点を再確認させる情報を送るのは、この不協和を和らげるためです。
人間関係における自己正当化
ある人を嫌いになりたいのに、その人の良い面を知ってしまったとき。
- 不協和の解消
「良い面もあるけど、やっぱりあの性格は受け入れられない」と、悪い面を過度に強調して、自分の嫌悪感を正当化する。