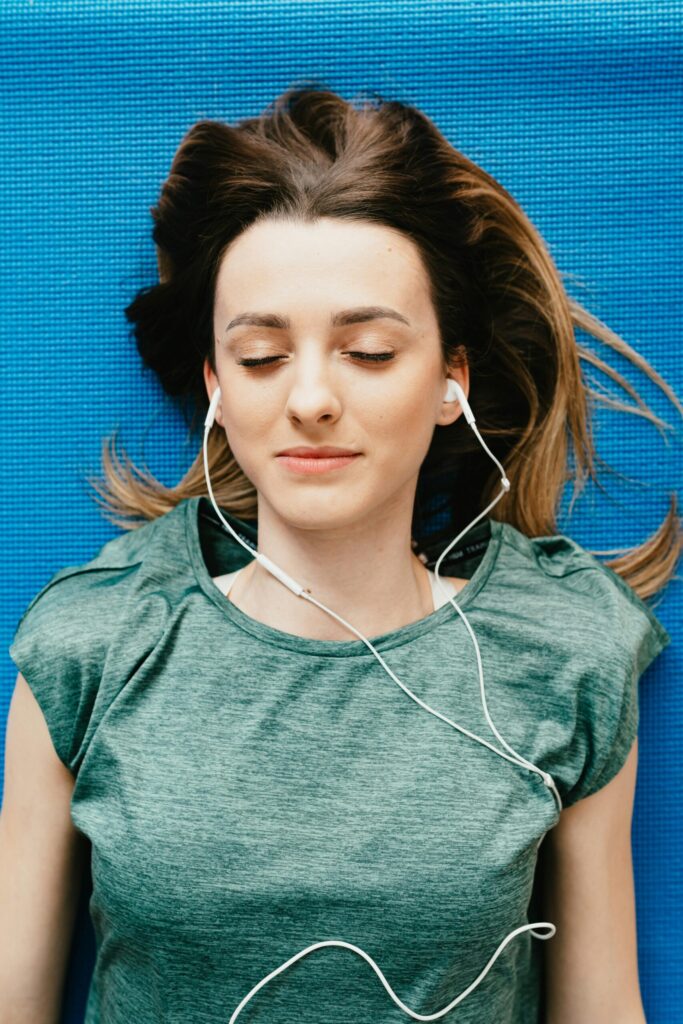「また、あおり運転のニュース…」「お店で怒鳴っている人がいる…」
最近、些細なことで激しく怒り出す人のニュースが後を絶ちません。肩がぶつかっただけなのに怒鳴られたり、ほんの些細な一言にいつまでもこだわられたり。あなたの周りにも、そんな「すぐキレる人」はいませんか?
「あの人の怒りは、ただの“性格”のせい…?」そう思って、諦めていませんか?
実はその怒りの裏側には、私たちも知らない「心の働き」や、大人になるまでの「環境」が深く関わっているとしたら…。
この記事では、最新のニュースを紐解きながら、その怒りの“正体”に迫ります。報道番組「ABEMA Prime」にも出演した専門家の見解も交え、原因から具体的な対策までを分かりやすく解説します。あなた自身や大切な人を守るヒントが、きっと見つかるはずです。
キレる脳の仕組み
結論から言うと、すぐキレる原因の一つは、脳の前頭葉(ぜんとうよう)の働きが関係しています。
前頭葉は、私たちの理性や思考、感情のコントロールを司る「脳の司令塔」のような場所です。計画を立てたり、我慢したり、相手の気持ちを考えたりする高度な働きを担っています。
この前頭葉は、10代を通じて成長し、20歳頃に完成すると言われています。つまり、この時期に適切な経験を積めないと、感情を抑える「脳のブレーキ」が効きにくい大人になってしまうのです。
原因は子供時代に?

では、なぜ前頭葉が十分に発達しないのでしょうか。その根っこは子供時代の環境にあることが多いのです。特に、以下の4つのポイントが大きく影響します。
感情の我慢と否定
意外に思われるかもしれませんが、甘やかされて育った子より、感情を我慢させられてきた子の方が、怒りを溜め込みやすくなります。泣いている子に「うるさい!泣き止みなさい!」と感情を無理やり抑えつけると、不満がたまったときに「怒り」という攻撃的な形でしか感情を表現できなくなってしまいます。
怒りっぽい親の真似
子どもは、最も身近な大人である親の行動を鏡のように真似して成長します。これは「ミラーニューロン」という神経細胞の働きによるもの。親がイライラしている環境では、子どもは「怒ること」が当たり前になっていくのです。
スマホ漬けの悪影響
今や子育ての必需品ともいえるスマホやタブレットですが、過度な依存は心のバランスを崩す原因になります。画面からの強い光や一方的な情報の洪水は、心を安定させる「セロトニン」という神経の働きを弱めてしまいます。
食生活の乱れ
「イライラしたら甘いもの」は、実は逆効果。空腹時にいきなり甘いものや菓子パンなどを摂ると血糖値が乱高下し、脳が興奮物質であるアドレナリンを分泌します。これが、強いイライラや攻撃的な感情につながるのです。